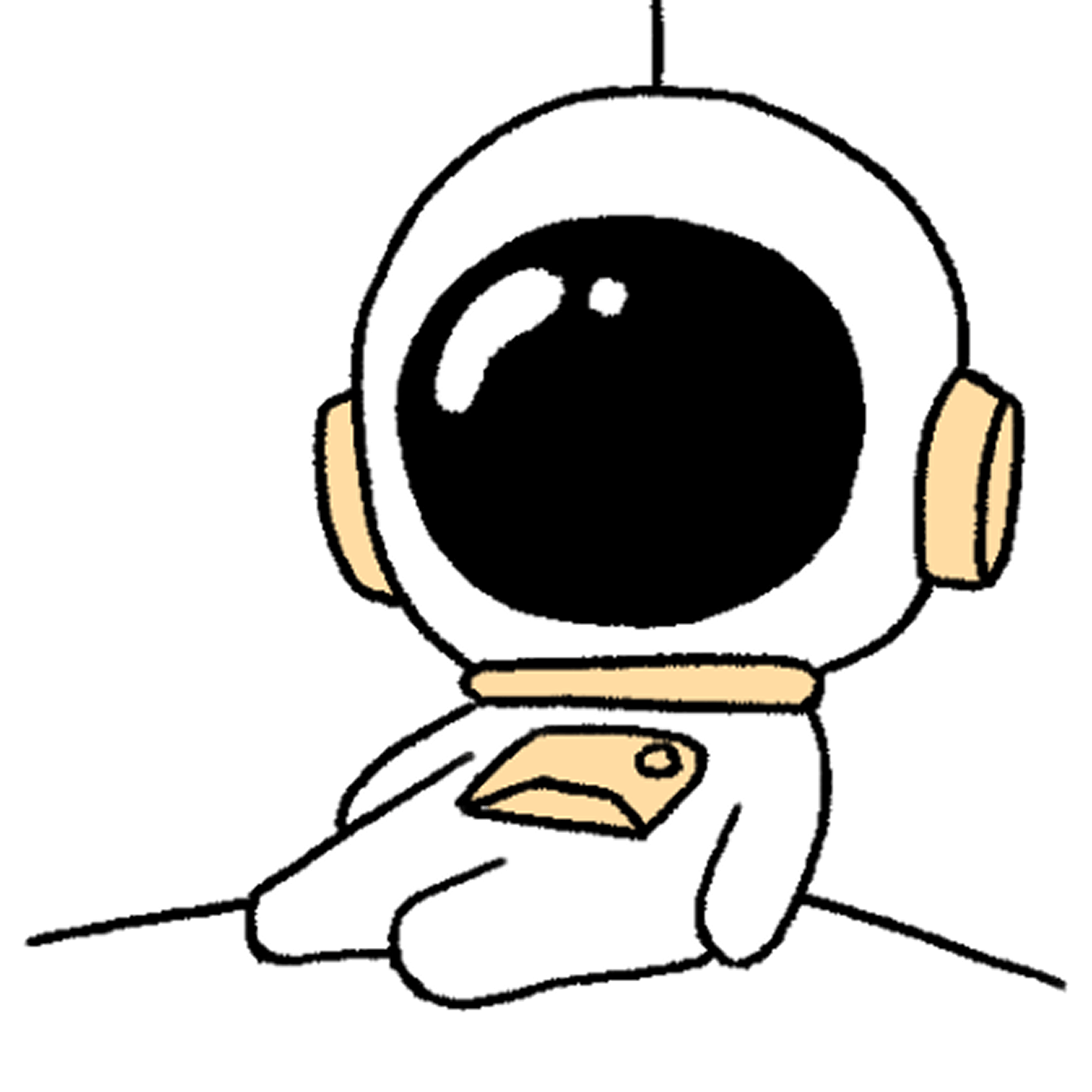アメジスト
読書記録です。
縄文時代の歴史
山田康弘 著
講談社現代新書
僕が住んでいる市内でも縄文時代の遺跡が見つかっているので、縄文時代の歴史についての本は読んでみたかったんですよね。
本書によると、土器の出現をもって縄文時代の始まりとし、灌漑水田稲作をもって弥生時代の始まりとするのが、定説だそうです。
土器の出現は最も古い場合は16500年前、灌漑水田稲作は最も古いのは、3000年前、または2400年前になり、その間が縄文時代ということになるそうです。
この時代は、狩猟、採集、漁労を主な生業とし、土器や弓矢を使い、本格的な定住生活も始まりました。
温暖な気候に恵まれ、栗林の育成(前期)、漆の採集(前期)、海水からの塩の精製(後晩期)などもおこなわれていたそうです。
特に、中期にあたる5470年くらい前から4420年くらい前に縄文時代の最盛期を迎え、日本列島全体の人口は26万人程度となり、西日本より東日本のほうが人口が多かったそうです。
また、縄文土器の一般的なイメージである派手で大ぶりな文様な付けられた土器や、有名な国宝の土偶「縄文のビーナス」は、この中期の時代に作られました。
東北地方において、精巧な亀ケ岡式土器や遮光器土偶を生み出した亀ケ岡文化が発達した時期が、晩期(3220年くらい前から2350年くらい前)となっています。
北海道の千歳市、恵庭市、苫小牧市などの石狩低地帯からは縄文時代後晩期につくったとみられる、周堤墓という大型の墓が発掘されているそうです。
周堤墓に埋葬される人/埋葬されない人の格差
周堤墓に埋葬される人々の中でも
周堤墓の中心部に埋葬される人/
周堤墓の内部空間に埋葬される人/
周堤上に埋葬される人/
という格差があったということが想定されるそうです
既にこの時代は単純な平等社会ではなく、すでに社会に階層が存在する「複雑化した社会」であった可能性が高いそうです。
縄文時代の人々は現代の意識高い系の方々が持っているようなサステナブルでエコロジカルで自然と共生しようという考えを持っていたというわけではなく、ごく少ない人口下で、石器によって人力で自然を切り開いていたので、開発の度合いよりも、自然の回復力の方が優っていただけというのが、この時代の真相だそうです。
#読書
#読書記録
#縄文時代
#先史学
#考古学

アメジスト
読書記録です。
カナダ
-資源・ハイテク・移民が拓く未来の「準超大国」
山野内勘二 著
カナダは大国だなあという認識はありましたが、食料自給率230%、エネルギー自給率180%と聞くと、改めて資源大国としての凄さを感じます。
日本でもマクドナルドのフライドポテトや小麦、キャノーラ油の原料である菜種、豚肉をカナダから輸入しており、日本の食卓はカナダが支えている面も大きいようです。
AIや量子コンピュータの開発も世界の最先端を走っているようで、大国として大きな可能性に満ち溢れた国なんだなと感じました。
今、Eテレで放送されているアニメ「アン・シャーリー」の舞台もカナダ東岸のプリンスエドワード島ですからね🇨🇦
魅力を感じる国です
#読書
#読書感想文
#カナダ
#地理
#国際

アメジスト
読書記録です。
観音 地蔵 不動
庶民のほとけ
頼富本宏 著
角川ソフィア文庫
僕の住んでいる地域の周辺では、地蔵信仰や不動信仰が行われているところがあるので、少し知ってみたいと思ったので、本書を読みました。
地蔵信仰は
地蔵菩薩の六道救済にちなんで六体の地蔵菩薩を集合させた六地蔵
三途の川の賽の河原で石塔を積む夭折した子供たちを守護する地蔵
戦で加勢してくれる地蔵
災難にあった時に身代わりになってくれる地蔵
寿命を伸ばしてくれる地蔵
田植えを手伝ってくれる地蔵
夏の地蔵盆が子供のための祭りという性格が強いのは、地蔵菩薩は子供のほとけという意味合いが濃いからであるようです。
千葉県の成田山は不動信仰の一大拠点で、江戸歌舞伎の初代市川團十郎は熱烈な不動尊信者で、不動尊に願をかけて長男の九蔵(二代目團十郎)を得たといい、そのためにますます不動尊の信仰を深め、自らが生身の不動尊を演じて大喝采を得ました。
その後、代々の市川團十郎は不動尊信仰の念篤く、市川團十郎の屋号が成田屋であるのは、ここに起因しているそうです。
勉強になりました。
不動明王が盗賊に金縛りをかけて懲らしめたという伝説があるそうで、不動明王はボディーガード的な性格があるようです。
地蔵信仰が交通事故で亡くなった犠牲者に弔うことに重点を置くことに対して、不動信仰は交通事故そのものを阻止することに重点を置くことに特徴があるようです。
#読書
#読書感想文
#地蔵
#不動
#信仰

アメジスト
読書記録です。
日本政治学史
丸山眞男からジェンダー論、実験政治学まで
酒井大輔 著
中公新書
想像以上に難解な内容でした。
政治に少し関心がある程度の心持ちだけで、政治学について読み解くのは無理ですね。
大まかな概要としては
20世紀後半における政治学は
「研究者の価値観」に基づく「過去や現状の分析」
そこでは「現状の分析」とともに「理念の追求」をも目指されたそうです
しかしながら21世紀に入ると
規範と実証、価値と事実を峻別し、
科学として純化するために
価値観を持ち込まず事実を明確しようとする方向性が強まったそうです
その一方で
「科学的」であることを目指すあまり
データは「(すでに演繹的に構築された)理論の正当性を検証するため」と位置づけられ
政治を「検証の素材」として扱われることが多くなっているそうです
素人の感想ですが
「権力の実態を明らかにすること」と
「望ましい社会を実現するため」にはどうすればいいのかを研究することを
両立してやればいいのではと思いました
#読書
#読書感想文
#政治学
#社会科学
#理念の追求

アメジスト
読書記録です。
ヤマト王権
吉村武彦 著
岩波新書
本書がカバーするのは、邪馬台国の時代から謎の4世紀を経て、倭の五王から継体、欽明の時代に仏教が伝来して古墳がつくられなくなる時代までのいわゆる古墳時代と呼ばれる時代です。
p86で述べられているとおり、「大王」号が後世の創作であるならば、倭王権の王は倭王と呼ぶのが妥当であるようです。
仁徳が河内王朝なのかどうかは、少なくとも古墳の発掘調査でもしないと、推測に推測を重ねる仮説しか言えないのが現状であり、つかみどころが難しい時代なんだなと感じました。
本書ではなぜか日本書紀がそうなっているからと理由で継体を応神五世孫と認めていますが、僕は信ぴょう性に乏しいと思います。
継体死後の二王朝並立や内乱の可能性についても否定する根拠は薄弱なように思います。
日本書紀や古事記と王家のある種の神聖性に引っ張られているように感じます。
#読書
#読書感想文
#古墳時代
#倭国
#倭王

アメジスト
読書記録です。
よりみち部落問題
角岡伸彦 著
ちくまプリマー新書
僕の住んでいる市内では部落問題というのは存在しないのですが、たまたまこの本が書店で目にとまり興味を持ったので、読んでみました。
著者は1963年生まれなので、世代的には「巨人・大鵬・卵焼き」「昭和元禄」「バブル景気」を謳歌した世代だと思うのですが、その影で非部落差別にルーツを持つ人間として、部落問題に関わり続けた半生を綴った内容となっています。
日本の差別問題について扱った博物館である「リバティおおさか」で働いていたという話は興味深かったです。
そのリバティおおさかは大阪維新の会によって潰されてしまったのは残念に思います。
保守政権というのは差別問題というのは自己責任だと切り捨てる特徴がありますが、維新の会というのはまさにその特徴にピッタリと当てはまります。
わかりやすい例えとして、
「障害者差別のない」社会を目指す方法として、
保守は障害者の「いない」社会を目指します。
リベラルは障害者が「差別されない」社会を目指します。
この違いは大きいです。
目指すべきは
部落出身者が「いない」社会ではなく、
部落出身を明らかにしても「差別されない」社会です。
それは、全ての差別問題に共通する問題です。
#読書
#読書感想文
#部落
#差別
#日本の暗部

アメジスト
午前中は散髪💈した後、時間があったので、お墓参り🪦もしました。
有意義に時間を使えました。
読書記録です。
サラブレッドはどこへ行くのか
「引退馬」から見る日本競馬
平林健一 著
NHK出版新書
引退した競走馬の大半は「食肉」になるということは知識の上では知っていますが、真正面から引退馬問題について論じているのは、本書が初めてだと思います。
単なる動物愛護ではなく、馬は本質的に「経済動物」であるという観点を持って、ターフを去った馬はどのように廃用されるのかということを丹念な取材によって明らかにしています。
競走馬というのは引退してしまうと経済的な価値がほとんどなくなってしまいます。
乗馬として売却しても安いですし、乗馬となった馬も早ければ数ヶ月で廃用されてしまいます。
繁殖用になった馬も繁殖用としての価値がなくなれば廃用されてしまいます。
人間にとっての使用価値は「食肉」にする以外になくなってしまうからです。
ターフのヒーローやアイドルになった馬が最終的に「食肉」となってしまう。
馬主や競馬の仕事で生活の糧を稼いでいる人などのホースマンも競馬ファンも馬肉は食べないというケジメを持つ必要があるように感じました。
#読書
#読書感想文
#競馬
#引退馬
#食肉

アメジスト
読書しました。
古墳と埴輪
和田晴吾 著
岩波新書
本書の考察で最も興味深かったのは、著者が「天鳥船(あまのとりふね)信仰」と名付けた古墳時代の他界観です。
死者の魂は鳥に誘われた船に乗って天上の他界へと赴き、そこで安寧な暮らしを送るというものだそうです。
古墳表面に並べられた埴輪は他界を表現したものであるというのが著者の見解です。
前回読んだ『埴輪は語る』(若狭徹 著 ちくま新書)とはまた違った解釈がなされており、いろいろな可能性が開かれている古代史の解釈の奥深さを感じます。
#読書
#読書感想文
#古墳
#埴輪
#いろいろな解釈

アメジスト
読書記録です。
「日本」とは何か
網野善彦 著
講談社学術文庫
「日本」は決して単一民族の国家ではなく、東日本と西日本は決して均質の国家ではなく、稲作中心社会ですらなかったということを、学術的に明らかにしようとしている内容となっています。
689年の浄御原令もしくは701年の大宝律令を持って「日本」の建国、天皇制度の成立とし、それ以前は倭国、倭王と呼ぶのが妥当であるというのは賛同します。
建国記念の日も架空の人物である神武天皇が即位したとされる2/11で本当に妥当がどうかというのも考えさせられました。
日の丸、君が代についても軍国主義の色がついていた歴史があるということは忘れてはいけないなと思いました。
鎌倉や江戸も源頼朝や徳川家康がいきなりつくった町ではなく、それ以前から海の交通の要衝として発展していた町であるという歴史があるということは勉強になりました。
第4章においては、百姓は農民だけではない、漁村もあり、瑞穂の国とは別の側面もある。
漁業を生業とする人々、廻船業、山間部の杣人(そまびと)や炭焼きの民、それから、養蚕業、商業、手工業者などがいて、年貢もコメだけではないという多様性のある国であるということを浮き彫りにして、瑞穂の国であるということを強調することは、本来、日本が持っている多様性が見えなくなる危険性があるということを論じています。
日本を天皇を中心とする国であると考えるのは、天皇が新嘗祭に代表される行事によって、「稲作文化」を中心に統べるということを強調することから、多文化共生に反する危険性があると思いました。
本書のタイトルである「日本」とは何かということを、あえて定義をするのは危険なことなのかもしれません。
#読書
#読書感想文
#歴史
#日本論
#多様性

アメジスト
承認ありがとうこざいます。
読書記録です。
埴輪は語る
若狭徹 著
ちくま新書
『日本書紀』には、殉死の風習を嘆いた乗仁天皇が、野見宿禰の意見を取り入れて出雲の土部(はじべ)に埴輪を作らせて古墳に置き、人の死に替わらせたする伝説が載っています。
しかしながら本書のp98の解説によると、考古学的には人物埴輪の登場が埴輪の中で最も遅いため、この説は否定的に捉えられており、ホッとしました。
この伝説は、古墳づくりや倭王の喪葬に関わった土師氏の祖先伝承として後付けされたものと考えられているそうです。
埴輪は、古墳の一画に据え置かれた展示物でした。
なかでも人物埴輪は、群像として配置されており、何らかのストーリーが込められていたと考えられます。
それを筆者は、古墳の主である「王」の治世のようすを、「絵巻物のように」ビジュアル化したものだとする説を唱えています。
第1章や第3章で、保渡田八幡塚古墳の埴輪を例に、人物埴輪は、王の祭祀、王の狩猟、王の武威、王の経済力を示したものであると考察されています。
著者は、古墳時代の王は、司祭者であり、武人であり、経済人であったので、王の多様な権能を表すために、様々な群像を配置したと解釈されています。
自然環境の変動は「神の仕業」と信じられていた古代において、地域の王は、民のために神を祀って環境を安定させ、悪神が里に災いをもたらさないように務める使命を帯びていました。
また、農地の実りを保証し、遠来の物資を確保し、最新技術を移入して地域を富ませなければならない宿命を負っていました。
埴輪群像は、この世を去った被葬者のそうした生前の事績を示し、それをみる共同体の人々に認知させるための仕掛けだったというのが、著者の結論となっています。
#読書
#読書感想文
#歴史
#古墳時代
#埴輪

アメジスト
読書記録です。
日米首脳会談
政治指導者たちと同盟の70年
山口航 著
中公新書
序章で解説されていた
首脳会談の「実質的機能」と「象徴的機能」の解説は勉強になりました。
首脳同士の個人的信頼関係の構築は重要なものであるらしく、だからこそ、わざとらしかろうが首脳同士がファーストネームで呼び合うのだそうです。
また、首脳間という最もハイレベルで合意することにより、相手国にその事項について約束させることが重要だそうです。
例えば、対日防衛義務を定めた日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用は、首脳レベルで約束させることに大きな意義があるそうです。
以上が首脳会談の「実質的機能」といわれるものです。
会談が開催され、意見の一致を再確認した、あるいは総理大臣が米大統領に伍して振る舞い自国にとって有利な取引を勝ち取ったとアピールするのは
日米間には信頼関係があることや政権支持率を上げることに繋がるアピールになる「象徴的機能」といわれるものです。
#読書
#読書感想文
#首脳会談
#外交
#信頼

アメジスト
読書記録です。
倭の五王
王位継承と五世紀の東アジア
河内春人 著
中公新書
ちょうど5世紀頃の倭の歴史について知りたかったので、勉強になりました。
当時の倭は朝鮮半島情勢に武力介入しており、想像以上に蛮族をしていたんだなと驚きました。
朝鮮半島南部からの鉄の供給に依存していたため、朝鮮半島情勢は倭にとって死活問題だったようです。
当時の倭は、古市古墳群をつくった王家と、百舌鳥古墳群をつくった王家と、継体大王を輩出した北陸系の王家と、三つの王家があって天下を持ち回りしていたという考察はなるほどなと思いました。
p225で述べられている、倭の五王の最後を飾る武が中国に遣使を行わなくなった5世紀後半から継体大王が登場する6世紀の初頭にかけては、倭国内は政治的に混乱していた可能性が高いという考察はなるほどなと思いました。
継体大王の登場は王朝の交代が行われていて、それに伴ってかなり混乱したという解釈が妥当なように思います。
p228によると
5世紀の倭の五王は、倭姓を名乗る王権が無姓の人々を治めていた。
6世紀の大王の王権は、姓を持たない王権が、豪族以下民衆にいたるまで姓を授けて、その上に君臨していた。
継体大王の時に、王朝交代劇が行なわれたのは明らかだと思います。
本書の冒頭で紹介されている七支刀が天皇家に伝えられていないことからも、倭の五王の王権とのちの天皇家は全く別の王権と解釈したほうがよさそうです。
5世紀の倭の歴史をより深く知るには、誉田御廟山古墳や大仙陵古墳を発掘調査する必要があるなと感じました。
天皇家の祖先ではない墓を祖先の墓だと言い張る宮内庁は非科学的な体質があるように感じます。
#読書
#読書感想文
#古代史
#倭国
#倭王権

アメジスト
読書記録です。
平城京の時代
坂上康俊 著
岩波新書
本書は奈良時代を中心とする8世紀の歴史を概説している内容となっています。
8世紀は、日本という国家が形を成しつつあった時代です。
国柄の基礎に仏教をおいたこと。
均田制をおこなうため、日本全国の水田を区画し直して、戦前までみられた一町四方の水田区画にしたこと。
律令制のもと戸籍による個別人身支配をしたこと。
ただ、共同体から離れた人たちを捕捉するのが困難となり、土地を帳簿と地図のセットで体系的に把握することを目指したこと。
律令国家の枠組みに天皇制度をはめ込んだこと。
唐から服装から社会制度から服装まで学び、自らの枠組みを整えていき、大宝律令という集大成のもとで、古代社会が成熟したのが、奈良時代であるといえそうです。
#読書
#読書感想文
#奈良時代
#律令国家
#古代

アメジスト
読書記録です
農耕社会の成立
石川日出志 著
岩波新書
弥生時代について
弥生時代のはじまりの基準は「灌漑稲作」である
灌漑水田は造成するのに、集落構成員による集中的な労働投下が必要
水利をめぐる利害調整をはかる必要がある
→集落内・集落間の調整が必要になる社会の質的な変化をもたらす契機となる
弥生時代の終わりの基準は「古墳の成立」である
定型的前方後円墳の出現
→西日本一帯に広く分布するようになるのは、首長の交替に伴う首長権継承儀礼が共有されるようになったからだと解釈できる
→広域にわたる首長どうしの政治的大連合が生まれいづる
弥生時代の諸事象
①灌漑稲作
九州(早期)から東北北部(前・中期)までおよぶ
→経済の質的変化
②環濠集落の役割・機能
⑴防御
⑵区画
⑶象徴
⑷集落構成員の内面的な結束
→社会の質的変化
③集団間の争い
北部九州に顕著で、中期後半以降は中部以西に認められる
④青銅器と鉄器
青銅器は北部九州が中心
→前期の末から中期のはじめにかけて
→有力者の副葬品
→祭祀の質的変化
鉄器は中期初頭以降に出現
→朝鮮半島東南部で鉄器生産が明確になる中期後半以降は、東日本にも普及
弥生時代で最も特徴的なのは
灌漑稲作
環濠集落
青銅器
#読書
#読書感想文
#弥生時代
#時代の画期
#身分格差の発生

アメジスト
読書記録です。
海賊の世界史
古代ギリシアから大航海時代、現代ソマリアまで
桃井治郎 著
中公新書
p12に載っているアレクサンドロス大王に捕らえられた海賊が、自分がやっていることは大王がやっていることと本質的に同じであり、一方は大艦隊でやっているので皇帝と呼ばれ、他方は小さい舟でやるので海賊と呼ばれているだけだという話は考えさせられます。
本書では西洋の海賊の歴史と並行して、ローマとカルタゴの戦争、イスラムによる征服と十字軍、レコンキスタ、オスマン帝国とスペイン帝国の覇権争い、スペインとイギリスによる新大陸侵略が述べられており、国家というのも略奪と戦争の歴史であり、テロリズムや海賊と本質的に同じであるということが認識できるようになっています。
トランプ大統領がやっている力の外交、覇権主義的な外交は、暴力性を伴っているという意味で国際テロリズムや海賊と同等であるということです。
公正といえる秩序なしに、大きな権力を持って世界を支配しようとするトランプ大統領こそがテロリストと言えるでしょう。
海賊には夢があります。
身分秩序からの自由
しがらみや社会的束縛からの解放
暴力装置で人民を抑圧する国家権力への反逆
様々な事柄が管理される現代だからこそ、海賊の秩序に対する反逆者、国家に対する個人としての側面、管理に対する自由の側面に魅力を感じます。
第4章の大航海時代やカリブ海の海賊列伝は百花繚乱で面白いです。
未知の世界である海の向こう側に、成功や名誉、冒険、自由を求めて戦った夢の物語です。
フランシス・ドレーク
ヘンリー・モーガン
キャプテン・キッド
ウッズ・ロジャーズ
バーソロミュー・ロバーツ
黒ひげティーチ
女海賊のアン・ボニーとメアリー・リード
などたくさんの海賊が紹介されています。
私掠行為は、国家の駆け引きである非公式の戦争だから、海賊たちに私掠船になるように勧めて、都合が悪くなると海賊たちは処刑されるという哀しさも知ることが出来て勉強になりました。
#読書
#読書感想文
#海賊
#世界史
#ロマン


浮沢
【この惑星で楽しみたいこと】
まぁぼちぼち
【最近のマイブーム】
パク・ミンギュ/ハン・ガンなどの韓国文学
岡江晃「宅間守精神鑑定書」

関連する惑星をみつける
お勉強の星
12120人が搭乗中
参加
語学学習の星
794人が搭乗中
参加
数学の星
737人が搭乗中
参加
数学の星では、文系な人も、理系な人も、数学得意苦手関わらず気軽に使ってくださいね✨️
医療学生の星
2889人が搭乗中
参加
医療学生さんのための惑星です👍🏻
みんなで分からないところや不安なところを語り合って医療従事者を目指しましょう💪🏻
勉強の星
9418人が搭乗中
参加
もっとみる