人気
初代ささみ後輩
今日1日で読破したけど
5章まではある程度予想通りの真犯人。
エピローグ読んだ瞬間にやられたー!!!ってなった。
設定は、地震で地下施設に閉じ込められて
脱出するには1人犠牲にしないといけない。
地下3階から水が流れ込んできてるから
脱出までの猶予は1週間。
そんな中で殺人が起こってもうめちゃくちゃ。
なんで?こんな状況なのに人殺しちゃうの?
え、2人目も!?殺し方が全然違うやん!
なんで?どうして??
早く犯人見つけてそいつを犠牲にして
脱出しないと!!!
って感じ。
おいおいまさかこいつが犯人じゃあるまいな?
いやいや、やめてくれ、こいつが犯人だとちょっとショックだよ…と感情移入して読んだら
見事!裏切られましたー!
これ読んだことある人、ぜひ感想を語り合いましょう。
#読書感想文 笑

アメジスト
今日、読んだ本です。
クラシック音楽の歴史
中川右介 著
角川ソフィア文庫
作曲家や曲などの紹介、雑学を99のテーマにして書いた本です。
一般的ななじみが薄くなる20世紀音楽についても言及されており、クラシック音楽について知る入門書としては、面白く書かれていていいと思います。
バロックから20世紀までのクラシック音楽の歴史を薄く広くざっくりとつかむにはいい本です。
#読書 #読書感想文 #クラシック音楽 #歴史

まゆし
誰かの死に対する後悔や思いに翻弄されて、残された人はどう歩み出すのか、そんな辛くも温かい短編集です
ちょっと人間関係が複雑だったり内容がハードめですが飽きずに読めました[穏やか]
短編集ですが、主人公が繋がっていて大筋が進んでいく感じです。
いつ何があるかわからないからこそ、後悔はなるべくないように生きたいそう思います
#読書感想文

アメジスト
読書記録です。
貴族とは何か
ノブレス・オブリージュの光と影
君塚直隆 著
新潮選書
著者は日本における英国史研究の第一人者で、特に第3章の英国貴族の歴史の記述は秀逸です。
英国貴族は王権と対峙してきたこと、税金を負担するかわりに統治権を手に入れたこと、貴族が重い課税負担を担っていたが故に、貴族による支配に一般市民が蜂起する市民革命が起こらなかったことが記述されています。
近代に入ってからは議会政治の担い手として、貴族制を保守するための改革を断行してきたこと、身を切る改革を断行して党派性に対しては超然とした態度をとってきたことで、21世紀に至るまで英国の貴族制は存続することが出来た、私利私欲に塗れる社会においてノブレス・オブリージュを担う階級を守ってきた、それが英国の強さである、ことなどが述べられています。
翻って日本では国家の選良である国会議員や富裕層は徳や公共精神を持ち合わせておらず、暗澹たる気持ちとなります。
本書の第4章第3項の結論部では、参議院を冷静な議論の府にするための改革の可能性について述べられており、国民の側も選挙における「義務投票制」を採用して国民としての責任をまっとうすることを要請することなどが述べられております。最後に、ひとりひとりの人間が、徳を重んじることの重要性を述べて結びとしています。
現代日本は、道徳を説くことが、最も無意味で愚かなおこないと疎まれ、冷笑される国でありますが、いにしえのギリシャ、ローマあるいは古代中華王朝などで徳を重んじて社会を主導した貴族たちがいた、「徳」の大切を説き続ける重要性を貴族の歴史が指し示しています。
#読書 #読書感想文 #貴族とは何か #徳と公共精神

アメジスト
読書記録です。
動乱の日本戦国史
桶狭間の戦いから関ヶ原の戦いまで
呉座勇一 著
朝日新書
新書らしい軽快なエンタテインメント性のある文章で面白く読めました。
戦国時代の主要な合戦をとりあげ、従来の通説がどのように形作られてきたか、作話の意図はなんだったのかを分析し、ここ30年ほどでどのように研究が進展したか、論点は何かと紹介されており、研究史の理解にも役に立ちます。
印象的に残ったのはまず、川中島の戦いにおける戦術家上杉謙信と戦略家武田信玄の対比です。戦いそのものは謙信側優勢で決着したものの、戦いが終わったあとが戦略家信玄の真骨頂の発揮で、実際に信州北部を勢力下に入れたのは甲相同盟を結び上杉方に対峙した信玄のほうだったというのはなるほどなと思いました。
桶狭間の迂回奇襲や長篠の三段撃ちというフィクションは信長神話を印象づけるために広まったものだということも納得しました。
ストーリーに酔って、歴史上の英雄を神話化することのワナにハマらないように気をつけないといけませんね。
本書の性格上、先行研究をわかりやすくまとめている章が多いですが、第7章については、「関東惣無事」は豊臣政権の武力介入を望む反北条連合をなだめるためのレトリックだという著者独自の見解は勉強になりました。
大阪の陣においては、家康は実は豊臣を滅ぼさずに臣従させることを目指していたというのは驚きました。
研究の進展によって新たな発見がうまれるというのは面白いです。
#読書
#読書感想文
#戦国時代
#合戦
#新説

アメジスト
読書をしました。
面白かったです。
植物に死はあるのか
生命の不思議をめぐる一週間
稲垣栄洋 著
SB新書
スラスラと読みやすく、植物の不思議な生態がよくわかりました。
プロローグで
いったい生命とは何なのだろう。
生きるとはいったいどういうことなのだろう。
それを考えた一週間だった。
と導入されているところから興味が惹かれました。
本書を読んで、生命が生きているということは本当に不思議なことなんだなと感じました。
植物というのも奥が深いです。
裸子植物と被子植物の違い、木と草の違いの本当の意味というのもはじめて知りました。
世代交代を早くする、確実にするために進化してきたんだなというのがわかりました。
エピローグで
与えられた命を生きて、与えられた死を受け入れるって素晴らしい
と締めくくられていたのはとても良かったです。
#読書
#読書感想文
#植物
#生命
#不思議

アメジスト
イタリアの歴史の本を読みました。
イタリアの通史の概要を学ぶのにちょうどよかったです。
一冊でわかるイタリア史
北原敦 監修
河出書房新社
監修者はイタリアの歴史の中でも特に近現代史を専門としていることもあり、19世紀の統一以降の記述が詳しいです。
第一次大戦からファシスト、第二次大戦にかけてのグダグダした歴史がわかりやすくまとめてあり、勉強になります。
#読書
#読書感想文
#歴史
#イタリア

アメジスト
読書記録です。
宇宙にはなぜ、生命があるのか
宇宙論で読み解く「生命」の起源と存在
戸谷友則 著
ブルーバックス
天文学や宇宙物理学の研究に取り組んできた著者が、シニアになってたどり着いた究極の難題「生命の起源」について考察した本です。
第1章では、「わずかに不完全な自己複製」が生命の本質として、生命とはなにかということをエントロピーの法則などの物理学の立場から説明しています。
第2章においては、核酸のメカニズムを中心として、生命の現象を化学や物理の法則から説明しており、生命現象の基本について学べる章となっています。
第3章においては、地球生命の進化史を駆け足で解説しており、地球の環境の変化と生命の進化はお互いに影響を与えあって営まれてきたということが強調されています。
第4章では宇宙の成り立ちについて解説されています。著者の専門であることもあり、コンパクトながらも専門的に解説されています。鉄より重い元素の合成は、超新星爆発や連星中性子星の合体など、かぎられた天体現象のみで実現する極限的な環境で起こることが知ることができ、勉強になりました。
第5章では、原始生命体が生まれるプロセスについて考察し、有力な仮説であるRNAワールドについて検証しています。
第6章では、物理学や化学の法則に従って原子や分子は淡々と動いたり反応したりするだけという自然科学の理論にもとづいて原始生命体の発生確率を見積もり、それがとてつもなく低い確率だということを考察しています。
第7章では逆転の発想で、インフレーション理論にもとづいた宇宙は非常に広大であることで、確率の問題は解決できると考察しています。
生命の起源問題についての現在地について。最新の物理学、化学、生物学の知見を駆使しても、現在いえることは、結局は確率論的な話に落ち着くということです。
宇宙の歴史のどの段階かはわからないけど、最初はただの物質から生命体がうまれた。それがどうやってできたのかは、現代科学の最新の知見を持ってしても見当がつかない。それがまさに生命の神秘ですね。
現代科学の限界と生命の神秘を知ることができて有意義な本でした。
#読書
#読書感想文
#生命
#宇宙
#神秘的

アメジスト
コーヒーを飲みながら、読書を楽しんでます。
ドリップ式コーヒーは美味しいですね。
今日読んだ本はこちらです。
西洋占星術史 科学と魔術のあいだ
中山茂 著
講談社学術文庫
西洋の占星術の歴史を古代バビロニアから書き起こして全体像を描いている本です。
古代ギリシアからローマにかけての占星術の発展の歴史について特に詳しく書かれていて面白いです。
中世ヨーロッパにおいて一旦衰えた占星術の伝統は、12世紀ルネサンスによって、占星術をアラビア語から翻訳し、大学で占星医学を教え、スコラ哲学が栄えました。
そのあと15世紀のルネサンスによってプラトン主義とともに占星術も復興します。
その後、ニュートン以降の近代物理学によって占星術は科学から脱落しましたが、現代に至るまで占星術の歴史は続いていて、人々の心に根差す星への憧れや未来を見通したいという願望に支えられています。
占星術の歴史というのは科学の歴史の重要な領域を占めているというのがわかります。
#読書 #コーヒー #読書感想文


アメジスト
読書しています。
新書100冊
視野を広げる読書
高橋昌一郎 著
光文社新書
新書は専門家が最新の知見を踏まえた考察を一般向けに書いた本が多く、知的好奇心が刺激されるので、僕も好んで読みますが、僕もこの本で紹介されている本の大半は読んでないですね。
歴史、哲学、政治、社会問題から科学系まで幅広い分野の本を取り上げており、著者はかなりの読書家だなと思いました。
ブルーバックスなどの理系の本も面白そうなので、積極的に読んでみたくなりました。
ブックガイドとして参考になる一冊です。
ただ著者自身の著作を5冊もいれたのは、やりすぎかなとは思いますが。
#読書
#読書感想文
#新書
#教養

ミナト
母「走れメロス読んだ?」
俺「一応読んだ。書いとくわ」
一年後
母「読書感想文とかやったん?」
俺「走れメロス思い出して書いといた」
一年後
母「読書感想文やった?」
俺「走れメロス思い出して書いといた」
母「あんたやるな」
ってエピソードをたまに思い出して今だに話す。
#読書感想文

メロス
アメジスト
読書記録です。
謎の平安前期
-桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年
榎村寛之 著
中公新書
専門的な内容を含んでいますが、9~10世紀の歴史の流れをつかめる好著です。
奈良時代に確立した、全国の土地を国有として、生産者に配って税収を上げる支配体制は、9世紀以降、国府が支配する国衙領と呼ばれる地域に限られる支配体制に変わっていった。
それ以外の地域は、地元の有力者が開拓した土地を大貴族や寺社に寄進した荘園となり、税を払わないという二重構造に変わっていく。
しかし彼ら荘園領主層もまた、大貴族や寺院に収入の一部を上納し、献物をして地位や名誉を得て、京で官位を得ていたことから、その収益も京へ回収されていった。
その意味で京と地方を結ぶ回路はより多様になり、物や人の動きはより活発になった。
新田の開発によって資産を増やした領主は、その資産を活用するために京に送る。
そして、物流の求心性が高まったことで、その核である京の消費文化が盛んになり、奈良時代より贅沢な王朝文化が花開いた。
8世紀には男性に伍して国家を支えていた女官たちのシステムはしだいに解体
↓
10世紀後半には、天皇と摂関家のお后候補として育てられた姫との結婚は、その実家になる摂関家有力者の争いとなる
かつてなら女官を目指せたような能力の高い女性たちは、女御や斎王の女房となる
↓
王朝時代の女性文学が華やかに発展したのは、女性が活躍できる場が少なくなり、サロンに集められて、本名もわからない活動をするようになったからである
#読書
#読書感想文
#歴史
#平安時代
#王朝文化

アメジスト
読書記録です。
フランス革命についての省察
エドマンド・バーク 著
二木麻里 訳
光文社古典新訳文庫
訳が秀逸で素晴らしい1冊です。
13の章に章立てされており、更に本文内に小見出しが添えてあり、とても読みやすくなっています。
凝った修辞が多い文章の特性をいかしつつ、現代日本語の読者に普通に読めるような文章になっているのは、訳者の力量の素晴らしさを感じます。
p188より抜粋
わたしたちは神を畏れます。畏敬をもって国王を見上げます。愛情をもって議会を見上げ、礼をもって為政者を見上げ、崇敬をもって聖職者を見上げ、尊重をもって貴族を見上げます。なぜでしょうか。それは、こうした観念が心に浮かぶときは、そんなふうに感じられるのが自然だからです。
バークのいう自然は、キリスト教の世界観に根ざしたものです。
なぜそれをたいせつにするかというと、先入観=prejudiceだからであると述べています。
このprejudiceはバーク思想の重要な鍵概念で、予めの判断という意味です。
先人の経験から受け継いだ知識や常識にもとづけば、未知の事象にも予めの判断力が働くという意味です。
時を経て磨かれてきた価値を尊重するというイギリス経験論の系譜にあるということがわかります。
経験の叡智を消滅させ、抽象的な啓蒙理念をもとに社会を再構築させるフランス革命のやりかたは、社会の転覆にとどまらず、道徳の転覆ももたらしてしまった。
これが近代の始まりだとすれば、近代というのは自然に反することをやり始めた時代だといえるのかもしれません。
近代化によって失われてしまったかもしれない、歴史や過去や、いま眼前にないなにものかの遠さのなかに真実をみようとする思想をもつこともたいせつなことなのかもしれないなと思いました。
#読書
#読書感想文
#バーク
#哲学
#思想

アメジスト
読書記録です。
西洋中世奇譚集成
妖精メリュジーヌ物語
クードレット
松村剛 訳
講談社学術文庫
本書は、クードレット作「メリュジーヌ物語」と、メリュジーヌ伝説に関する近年の関心の端緒になったジャック・ルゴフとエマニュエル・ルロワ=ラデュリの論考「母と開拓者としてのメリュジーヌ」の全訳からなっています。
「メリュジーヌ物語」はいわゆる異類婚姻譚で、中世ヨーロッパの不思議な魅力が詰まっています。
次々と展開が進んでいく物語なので、飽きずに読むことができます。
まえがきで簡単にストーリーを予習できるようになっており、ストーリーもおとぎ話のように楽しめる内容になっています。
後半では民俗学的見地から、中世と近世それぞれで「メリュジーヌ」伝説がどのように受け取られてきたのかを論考しています。
もともとはクードレットは、パルトネ領主ギヨーム・ラルシュヴェックのためにこの作品を書いたもので、中世においてはメリュジーヌは一族のルーツ、多産と子孫繁栄の象徴としてとらえられていました。
それが時代がくだると、村の年寄りが語り継ぐ伝説となり、メリュジーヌのイメージも農業繁栄へ変遷していったという考察が面白かったです。
#読書
#読書感想文
#中世ヨーロッパ
#メリュジーヌ

アメジスト
こんばんは。
お盆明け、今日の仕事は順調でした。
休みの日に本をもう1冊読んでいたので、読書感想文を書きます。
ごまかさないクラシック音楽
岡田暁生
片山杜秀 著
新潮選書
帯には入門書とありますが、博識のお二方が様々な観点から話を進めて、二人のホンネが語られるので刺激的な対談となっています。
ベートーヴェンの音楽はみんなで頑張ろう、頑張ったぶんだけ明日は今日より良くなるという精神をうたったものだからこそ、コロナ禍でよく演奏されたというのが理解できます。
人類が滅亡する世界で奏でられるのに相応しいのはバッハの音楽だという話も面白いと思います。バッハは神の秩序を自分の音楽で表現しようとしていた、神の秩序を一人で引き受けたという意味でまさに「音楽の父」といえます。
作曲家のバックボーンについて語られているので、知的好奇心を刺激する面白い内容となっています。
#おつかれGRAVITY
#読書
#読書感想文
#クラシック

アメジスト
読書記録です。
矢部貞治
知識人と政治
井上寿一 著
中公選書
本書は先行研究や「矢部日記」をなぞるかたちで、矢部貞治(やべていじ、1902~67)の評伝を綴った本です。
矢部は戦前は東京帝国大学教授(政治学講座)を務め、近衛文麿の昭和研究会に参加したり、海軍のブレーンとして活動しました。戦後は在野の知識人として、あるいは拓殖大学総長を務めたりしながら、政治評論家としてあるいは憲法調査会などの審議会のメンバーとして活動しました。
戦前の統帥権問題や戦後の憲法改正問題、あるいは二大政党制のありかたについての矢部の提言は、現代を生きる私たちも傾聴に値いするものがあります。
デモクラシーの発展のため、国民の下からの政治運動をおこなう、これが矢部の考える知識人としての使命であり、生涯をかけて政治にコミットした動機というのが露わになったのが本書の意義であるように思います。
#読書 #読書感想文 #矢部貞治

新着
アメジスト
読書記録です。
カナダ
-資源・ハイテク・移民が拓く未来の「準超大国」
山野内勘二 著
カナダは大国だなあという認識はありましたが、食料自給率230%、エネルギー自給率180%と聞くと、改めて資源大国としての凄さを感じます。
日本でもマクドナルドのフライドポテトや小麦、キャノーラ油の原料である菜種、豚肉をカナダから輸入しており、日本の食卓はカナダが支えている面も大きいようです。
AIや量子コンピュータの開発も世界の最先端を走っているようで、大国として大きな可能性に満ち溢れた国なんだなと感じました。
今、Eテレで放送されているアニメ「アン・シャーリー」の舞台もカナダ東岸のプリンスエドワード島ですからね🇨🇦
魅力を感じる国です
#読書
#読書感想文
#カナダ
#地理
#国際


ふーびぃ
万人におすすめしたい内容でした☆
すごくいいなーと思ったのは、「自分を知る」ことに焦点を当てていること。
ぼんやりとでもいいから自分を知って、自分の好きな方向にベクトルを決めて動いていけば自分のやりたいことに出会える可能性も高くなると思う。
これからもまだまだ理解しきれてない自分を探し続けるんだろうなー♫
#世界一やさしいやりたいことの見つけ方
#八木仁平
#読書感想文


ふーびぃ
著者の河野玄斗氏(通称げんげん)は「頭脳王」という番組で数ある天才たちの中でも飛び抜けて天才っぷりを発揮していたので、気になって行方を追っていたら本も書いたしYou Tuberにもなってたw
・勉強はコスパのいい最強の遊び
・人生の最大幸福化を目指すために勉強はとても便利
ということを特に伝えたいんだろうなという感じですね。
確かにシンプルにまとまってるし、効果があるだろうこともわかる。
結局はそれをやるかやらないかってことっすね。
今の時代は情報や答えが山のようにあるから、行動したもん勝ちな感じですねー‹‹\(´ω` ๑ )/››
#シンプルな勉強法
#読書感想文
#河野玄斗


ふーびぃ
2つの物語から成る本書。
芸人のラランドにハマっているので、ニシダが書いた本は読んでみたいと思ったので手に取る。
最初は独特の言い回しで読みづらい本だと思ったが、正直そこがニシダらしいとも思う。
表題の「ただ君に〜」の方が物語に入っていける。
うーん、この物語をどう咀嚼するのがいいか頭でぐるぐるする。
小説って答えもないし感じ方も捉え方もひとつじゃないし、そこが醍醐味だと思う。
読み終えて思うのは「ただ君に幸あらんことを」。
虚像かもしれないが、物語の人物にそう思わせていただきました。
#ただ君に幸あらんことを
#読書感想文
#ニシダ


ふーびぃ
★★★★☆「本を読まなくてもなんとかなる時代。だからこそ本を読もう!」
すぐに正解が転がっている現代だからこそ、脳の「スロー思考」を働かせることが重要。
※「ファスト&スロー参照」
具体的にどう1枚にまとめていくかは、本書を読んでください(笑)
少し話すと、「なんのためにこの本を読むのか?」、「読んだ結果どのように行動や考えを変えるのか?」を紙に書き出し、整理していく。
そこを抑えていけば、「紙一枚」にこだわらなくても読書の意味も変わるし、考えも深まっていく。
簡単にまとめるとそんな感じですね☆
最近はインプット過多だったので、ちゃんとアウトプットしなきゃなーって思うのと、アウトプットを意識してインプットしなきゃなーと思うこの頃です(ง ᵕωᵕ)ว♪
#読書感想文
#浅田すぐる

アメジスト
読書記録です。
日米首脳会談
政治指導者たちと同盟の70年
山口航 著
中公新書
序章で解説されていた
首脳会談の「実質的機能」と「象徴的機能」の解説は勉強になりました。
首脳同士の個人的信頼関係の構築は重要なものであるらしく、だからこそ、わざとらしかろうが首脳同士がファーストネームで呼び合うのだそうです。
また、首脳間という最もハイレベルで合意することにより、相手国にその事項について約束させることが重要だそうです。
例えば、対日防衛義務を定めた日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用は、首脳レベルで約束させることに大きな意義があるそうです。
以上が首脳会談の「実質的機能」といわれるものです。
会談が開催され、意見の一致を再確認した、あるいは総理大臣が米大統領に伍して振る舞い自国にとって有利な取引を勝ち取ったとアピールするのは
日米間には信頼関係があることや政権支持率を上げることに繋がるアピールになる「象徴的機能」といわれるものです。
#読書
#読書感想文
#首脳会談
#外交
#信頼

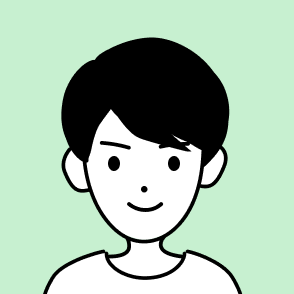
ととと
社会という集団の中で生きていくためには、大多数と良好な関係を築く必要がありますが、そのためにはまず大多数から好かれる必要があります。
誰かに好かれるために興味のないことでも好きだと言ってみたり、相手の言うことをなんの抵抗もなく全肯定してみたり。
方法は様々ですが、ありのままの自分を愛してもらえる人というのは酷く少ないのではないでしょうか。
誰もが何かどこかを繕いながら、不完全な自分をそれでも尚愛してもらえるように見せかける。
私はそれを悪いことだとは思いません。
とはいえ、「作り物の自分」が愛されたからといって、それは本当に「自分」が愛されていると言えるのでしょうか?
自分が隠していること、偽っていることを『腹を割って』話したとして、そこから溢れ出てくるのは本音でも本心でも何でもなくただ両者の痛みのみではないでしょうか。
そうなのであればお互いに本心は隠したまま、誰かに好かれる自分という外皮だけで関係を続けていくという方がよっぽど健全なような気もします。
自分を偽って生きるというのは、自分の弱みを隠して生きているように思われますが、あるいはその行為自体が弱みになるのかもしれません。自分を隠そうとする人はどこかに恐怖心があると思うんです。
「自分の性格が嫌われたらどうしよう」「自分の好きな物が否定されたらどうしよう」、そんな恐怖があるから中々自分を曝け出せずに結局は自分を押し殺してしまう。
その結果、自分の好きな物も忘れて、その中に残るものはただ「愛されたい」という自分だけ。自分を守るために始めたはずのそれに、気がつけば自分が殺されてしまっている。本作の主人公もきっとそんな感じだったのではないでしょうか。
誰かに好かれたい、と思うのは当然の考えですが、あくまでもそれは手段であって目的ではありません。自分を守るために、自分の好きを共有するために誰かに愛される必要があったのに、誰かに愛されることに躍起になって、なぜ愛されたかったのかも忘れてしまうと「愛されたい」だけが残った醜い化け物に成り果てます。
けれど多分、作り物の、上辺だけの自分を愛してくれる人の愛もまた、上辺だけのものなのでしょうね。
#読書感想文 #読書 #読了


ふーびぃ
★★★★☆「他の誰に負けてもいいが、自分にだけは、負けるな」
おもろかった!
ラノベだけど、「もっと学びたい!」と思わせる力は十二分に持っている作品と思いますね。
「ちゃんと戦って負けることは尊いことだ」って、結構人生において重要なことだと思うんですよ。
自分の大きさや能力を知るためには、どっかで躓いておかないと勘違いが起きるんよね。
「勉強をするほど、世界の解像度が上がる」という一文もとても大切なことかと。
でも、この文章は本気で勉強した人じゃないと理解できないし、響かないんだろうなぁ(^^ゞ
まだまだ、知らないことばっか。
まだまだ、勉強し続けたいですなぁ。
#読書感想文
#庵田定夏

アメジスト
読書記録です。
日本政治学史
丸山眞男からジェンダー論、実験政治学まで
酒井大輔 著
中公新書
想像以上に難解な内容でした。
政治に少し関心がある程度の心持ちだけで、政治学について読み解くのは無理ですね。
大まかな概要としては
20世紀後半における政治学は
「研究者の価値観」に基づく「過去や現状の分析」
そこでは「現状の分析」とともに「理念の追求」をも目指されたそうです
しかしながら21世紀に入ると
規範と実証、価値と事実を峻別し、
科学として純化するために
価値観を持ち込まず事実を明確しようとする方向性が強まったそうです
その一方で
「科学的」であることを目指すあまり
データは「(すでに演繹的に構築された)理論の正当性を検証するため」と位置づけられ
政治を「検証の素材」として扱われることが多くなっているそうです
素人の感想ですが
「権力の実態を明らかにすること」と
「望ましい社会を実現するため」にはどうすればいいのかを研究することを
両立してやればいいのではと思いました
#読書
#読書感想文
#政治学
#社会科学
#理念の追求


ふーびぃ
その原動力が、「ただ描くのが好きだから」っていう人は放っておいても成長するはず。
ただ、成長の質を上げるためには、知識のインプットも重要。
そういうインプット/アウトプットを上手く回していけたら気がついたら素敵な絵が描けるんでしょうね☆
僕自身あんまり絵を描く機会はないんだけど、こういうアーティスティックな分野も他の勉強と一緒で、「インプット2割、アウトプット8割」くらいのバランスで実践できたらいいんだろうなー。
久々に絵を描いてみるのもえーかもなぁ\( ˊωˋ )/
#読書感想文
#絵が上手くなる5つの習慣
#暁まゆる


ふーびぃ
とりあえず「はじめに」の部分だけでいいので読んでみてください(笑)
自分はそんなテンションで読み始め、すぐ引き込まれ、気がついたら全部読んでました(^^ゞ
芸人の方が書いた本なので、教科書で書かれているようなお堅い言葉は一切なし!全編爆笑!
ちょっとハマってしまって、数日後には「戦国無双4」を購入するほど戦国時代好きになってしまったので、「こうはなりたくないな」って人はむしろ読まない方がいいです(笑)
でも、みんなに読んでほしいなー。
#読書感想文
#超現代語訳戦国時代
#房野史典

アメジスト
読書記録です。
よりみち部落問題
角岡伸彦 著
ちくまプリマー新書
僕の住んでいる市内では部落問題というのは存在しないのですが、たまたまこの本が書店で目にとまり興味を持ったので、読んでみました。
著者は1963年生まれなので、世代的には「巨人・大鵬・卵焼き」「昭和元禄」「バブル景気」を謳歌した世代だと思うのですが、その影で非部落差別にルーツを持つ人間として、部落問題に関わり続けた半生を綴った内容となっています。
日本の差別問題について扱った博物館である「リバティおおさか」で働いていたという話は興味深かったです。
そのリバティおおさかは大阪維新の会によって潰されてしまったのは残念に思います。
保守政権というのは差別問題というのは自己責任だと切り捨てる特徴がありますが、維新の会というのはまさにその特徴にピッタリと当てはまります。
わかりやすい例えとして、
「障害者差別のない」社会を目指す方法として、
保守は障害者の「いない」社会を目指します。
リベラルは障害者が「差別されない」社会を目指します。
この違いは大きいです。
目指すべきは
部落出身者が「いない」社会ではなく、
部落出身を明らかにしても「差別されない」社会です。
それは、全ての差別問題に共通する問題です。
#読書
#読書感想文
#部落
#差別
#日本の暗部

アメジスト
午前中は散髪💈した後、時間があったので、お墓参り🪦もしました。
有意義に時間を使えました。
読書記録です。
サラブレッドはどこへ行くのか
「引退馬」から見る日本競馬
平林健一 著
NHK出版新書
引退した競走馬の大半は「食肉」になるということは知識の上では知っていますが、真正面から引退馬問題について論じているのは、本書が初めてだと思います。
単なる動物愛護ではなく、馬は本質的に「経済動物」であるという観点を持って、ターフを去った馬はどのように廃用されるのかということを丹念な取材によって明らかにしています。
競走馬というのは引退してしまうと経済的な価値がほとんどなくなってしまいます。
乗馬として売却しても安いですし、乗馬となった馬も早ければ数ヶ月で廃用されてしまいます。
繁殖用になった馬も繁殖用としての価値がなくなれば廃用されてしまいます。
人間にとっての使用価値は「食肉」にする以外になくなってしまうからです。
ターフのヒーローやアイドルになった馬が最終的に「食肉」となってしまう。
馬主や競馬の仕事で生活の糧を稼いでいる人などのホースマンも競馬ファンも馬肉は食べないというケジメを持つ必要があるように感じました。
#読書
#読書感想文
#競馬
#引退馬
#食肉

アメジスト
読書記録です。
平城京の時代
坂上康俊 著
岩波新書
本書は奈良時代を中心とする8世紀の歴史を概説している内容となっています。
8世紀は、日本という国家が形を成しつつあった時代です。
国柄の基礎に仏教をおいたこと。
均田制をおこなうため、日本全国の水田を区画し直して、戦前までみられた一町四方の水田区画にしたこと。
律令制のもと戸籍による個別人身支配をしたこと。
ただ、共同体から離れた人たちを捕捉するのが困難となり、土地を帳簿と地図のセットで体系的に把握することを目指したこと。
律令国家の枠組みに天皇制度をはめ込んだこと。
唐から服装から社会制度から服装まで学び、自らの枠組みを整えていき、大宝律令という集大成のもとで、古代社会が成熟したのが、奈良時代であるといえそうです。
#読書
#読書感想文
#奈良時代
#律令国家
#古代


ふーびぃ
とても評価されている本だったので読んでみる。
「衝撃の1行」があるらしく、どこで衝撃が来るのかなーと思っていたら確かに衝撃があった。
混乱して前半を読み返しちゃいましたし(^^ゞ
ただ、期待しすぎたせいか少し物足りなさを感じてしまったのも事実。
人によって合う合わないはあると思うので、自分としてはこれくらいの評価だなという感じかなー。
いや、めちゃ面白かったですよ?(笑)
#読書感想文
#十角館の殺人
#綾辻行人

アメジスト
読書記録です。
ヤマト王権
吉村武彦 著
岩波新書
本書がカバーするのは、邪馬台国の時代から謎の4世紀を経て、倭の五王から継体、欽明の時代に仏教が伝来して古墳がつくられなくなる時代までのいわゆる古墳時代と呼ばれる時代です。
p86で述べられているとおり、「大王」号が後世の創作であるならば、倭王権の王は倭王と呼ぶのが妥当であるようです。
仁徳が河内王朝なのかどうかは、少なくとも古墳の発掘調査でもしないと、推測に推測を重ねる仮説しか言えないのが現状であり、つかみどころが難しい時代なんだなと感じました。
本書ではなぜか日本書紀がそうなっているからと理由で継体を応神五世孫と認めていますが、僕は信ぴょう性に乏しいと思います。
継体死後の二王朝並立や内乱の可能性についても否定する根拠は薄弱なように思います。
日本書紀や古事記と王家のある種の神聖性に引っ張られているように感じます。
#読書
#読書感想文
#古墳時代
#倭国
#倭王

アメジスト
読書記録です
農耕社会の成立
石川日出志 著
岩波新書
弥生時代について
弥生時代のはじまりの基準は「灌漑稲作」である
灌漑水田は造成するのに、集落構成員による集中的な労働投下が必要
水利をめぐる利害調整をはかる必要がある
→集落内・集落間の調整が必要になる社会の質的な変化をもたらす契機となる
弥生時代の終わりの基準は「古墳の成立」である
定型的前方後円墳の出現
→西日本一帯に広く分布するようになるのは、首長の交替に伴う首長権継承儀礼が共有されるようになったからだと解釈できる
→広域にわたる首長どうしの政治的大連合が生まれいづる
弥生時代の諸事象
①灌漑稲作
九州(早期)から東北北部(前・中期)までおよぶ
→経済の質的変化
②環濠集落の役割・機能
⑴防御
⑵区画
⑶象徴
⑷集落構成員の内面的な結束
→社会の質的変化
③集団間の争い
北部九州に顕著で、中期後半以降は中部以西に認められる
④青銅器と鉄器
青銅器は北部九州が中心
→前期の末から中期のはじめにかけて
→有力者の副葬品
→祭祀の質的変化
鉄器は中期初頭以降に出現
→朝鮮半島東南部で鉄器生産が明確になる中期後半以降は、東日本にも普及
弥生時代で最も特徴的なのは
灌漑稲作
環濠集落
青銅器
#読書
#読書感想文
#弥生時代
#時代の画期
#身分格差の発生


ふーびぃ
★★★★★「キャリアに悩む全ての人々へ」。
自分は何が向いているのか。何がしたいのか。これからどうすればいいのか。
そういった疑問に具体的な道筋を示してくれる本書。
数学的な考え方で曖昧なものを具体的・体系的にまとめ、ものごとの「考え方」を伝えてくれる。「就職は不正解を選ばなければ正解」など、確かに振り返ってみればそうだったかもしれない。
今苦しんでいる人もいつか絶対何とかなる。そして、「人生は自分で選べる」だということを思い出してほしい。自分も苦しんでいる人に寄り添えるように在りたいと思う。
真面目に感想書いちゃった(^^ゞ

アメジスト
読書記録です。
「日本」とは何か
網野善彦 著
講談社学術文庫
「日本」は決して単一民族の国家ではなく、東日本と西日本は決して均質の国家ではなく、稲作中心社会ですらなかったということを、学術的に明らかにしようとしている内容となっています。
689年の浄御原令もしくは701年の大宝律令を持って「日本」の建国、天皇制度の成立とし、それ以前は倭国、倭王と呼ぶのが妥当であるというのは賛同します。
建国記念の日も架空の人物である神武天皇が即位したとされる2/11で本当に妥当がどうかというのも考えさせられました。
日の丸、君が代についても軍国主義の色がついていた歴史があるということは忘れてはいけないなと思いました。
鎌倉や江戸も源頼朝や徳川家康がいきなりつくった町ではなく、それ以前から海の交通の要衝として発展していた町であるという歴史があるということは勉強になりました。
第4章においては、百姓は農民だけではない、漁村もあり、瑞穂の国とは別の側面もある。
漁業を生業とする人々、廻船業、山間部の杣人(そまびと)や炭焼きの民、それから、養蚕業、商業、手工業者などがいて、年貢もコメだけではないという多様性のある国であるということを浮き彫りにして、瑞穂の国であるということを強調することは、本来、日本が持っている多様性が見えなくなる危険性があるということを論じています。
日本を天皇を中心とする国であると考えるのは、天皇が新嘗祭に代表される行事によって、「稲作文化」を中心に統べるということを強調することから、多文化共生に反する危険性があると思いました。
本書のタイトルである「日本」とは何かということを、あえて定義をするのは危険なことなのかもしれません。
#読書
#読書感想文
#歴史
#日本論
#多様性

もっとみる 
関連検索ワード
